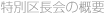
特別区制度の概要
◇ 特別区制度とは
東京都内には62の市区町村があります。その中で、23区は「特別区」と呼ばれています。特別区は、それぞれ公選の区長、議会や条例制定権、課税権を持ち、一般の市町村と同じ基礎自治体です(大阪市や横浜市などの政令指定都市にある「区」は、行政区といい、市の内部機構であり、自治体である特別区とは性格もしくみも異なります)。
一方、東京23区の区域は、970万人を超える人びとが暮し、1300万人近い人びとが活動する巨大な大都市地域です。人口や産業が高度に集積するこの地域の行政は、全体として滞りなく円滑に行われる必要があります。
このため、それぞれの特別区が身近な自治体として基本的な役割を担いつつ、広域自治体である東京都との役割分担のもとに、相互に連携して東京大都市地域の行政に責任を持つ特別な大都市制度が設けられています。この仕組みを都区制度あるいは特別区制度と呼んでいます。
通常は市が行う上下水道や消防などを都が実施することや、都と23区間の財政調整の仕組みがあること、また、都区間及び特別区間の連絡調整を行うための法定の協議組織が設けられていることなどが特徴です。
◇ 都区の役割分担と財源の調整
特別区は、東京大都市地域の基礎自治体として、区民に身近な行政を担っています。しかし、この大都市地域全体を一体として処理する必要がある事務もあり、通常は市が行う事務のうち例外的に東京都が処理しているものがあります。たとえば、水道、下水道、消防、大規模な都市計画などです。
一方、特別区の区域は23の基礎自治体でひとつの大都市地域を構成していますが、区ごとに見ると、その税源は大きく偏在しています。
このため、東京都と特別区が役割分担に応じて財源を分け、また23区の税源の偏在を調整して、それぞれが均衡ある行政を行えるようにするための制度として、都区間と特別区相互間の財政調整を行う仕組みが設けられています。これを都区財政調整制度と言います。
この財政調整を行うための財源として、通常は市町村税であるもののうち、固定資産税や法人住民税等が都税とされています。東京都と特別区は、毎年財政調整のための協議を行っています。
なお、地方公共団体間の財政調整の仕組みとしては、地方交付税制度がありますが、この制度の中では、都と特別区は一括して算定され(ただし、収入超過と計算され不交付)、都と個々の23区の調整については、都区財政調整制度を通じて行うこととされています。
(詳しくは、都区財政調整制度のあらましをご参照ください)